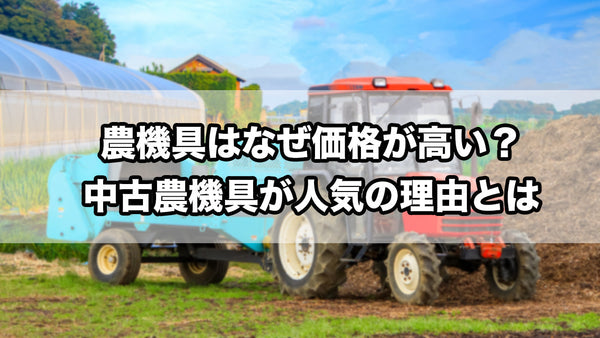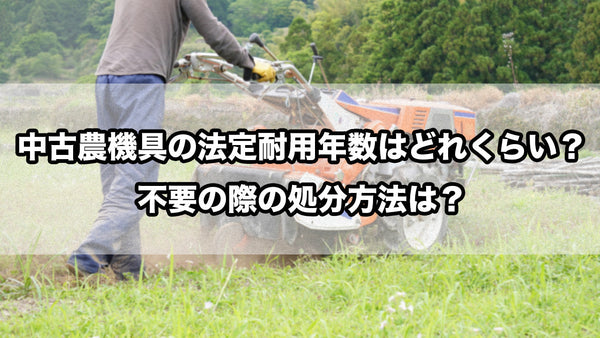じゃがいもは多くの人に愛される食材であり、その栽培は手軽で楽しい趣味として広く行われています。しかし、じゃがいもの栽培にはさまざまな病害が潜んでおり、これらの病害が放置されると収穫に大きな影響を及ぼすことがあります。本記事では、じゃがいもの正しい栽培方法および主要なじゃがいもの病害とその具体的な対策方法について詳しく解説します。これからじゃがいもを育てようとしている農家の方にとって、これらの知識は収穫の成功に不可欠です。
1. じゃがいもの特徴
じゃがいもの栄養素や調理方法を理解することで、食事の豊かさと健康への貢献が期待できます。また、栽培方法を知っておけば、経済的にもメリットがあり、自家製の食材で食費を節約できます。さらに、多彩な調理法を活用することで、食事のバリエーションが増え、食卓が楽しみになります。持続可能な農業の理念に基づく栽培に取り組むことで、持続可能性への理解が深まります。自給自足の満足感や地域社会への貢献感も得られ、新しい趣味やライフスタイルを開発する一助となります。要するに、じゃがいもに関する知識は、食事、経済、持続可能性、趣味、社会貢献など多くの面でメリットをもたらします。ここからが、じゃがいもの栄養素や調理方法について説明します。
栄養素
まずは、じゃがいものもつ栄養素について説明します。

食物繊維:第六の栄養素
食物繊維は、私たちの体にエネルギー源としては役立たないものの、健康を維持するために不可欠な成分です。これは通常「第六の栄養素」とも呼ばれています。一般的な五大栄養素には炭水化物、脂質、タンパク質、ビタミン、ミネラルが含まれます。
食物繊維は、水に溶けやすい水溶性食物繊維と水に溶けにくい不溶性食物繊維に分けられます。水溶性食物繊維は、食事後の血糖値上昇を緩やかにし、血中コレステロール値を低下させ、高血圧を予防する助けになります。一方、不溶性食物繊維は、水分を吸収して便のかさを増やし、有害物質を排除し、腸内環境を改善します。じゃがいもには、水溶性と不溶性の両方の食物繊維が豊富に含まれているため、糖尿病などの生活習慣病の予防と腸内環境の改善の両方の効果を期待できます。
抗酸化作用を持つビタミンC
ビタミンCには強力な抗酸化作用があり、肌の健康をサポートし、シミやくすみの原因となる活性酸素を排除する助けになります。また、ビタミンCはコラーゲンの生成を促進し、健康な肌の維持にも寄与します。100gあたりのじゃがいもに含まれるビタミンCは28mgで、同じ重さのみかんに含まれる量の80%に相当します。自家栽培のじゃがいもから取れるビタミンCを活用して、健康的な肌を保つことができます。
高血圧予防に効果的なカリウム
カリウムはミネラルの一種で、ナトリウム(塩分)の排泄を助け、高血圧を予防するのに役立ちます。カリウムは腎臓でナトリウムの吸収を抑制し、尿中に排泄させて血圧を下げる効果があります。じゃがいもの100gあたりに含まれるカリウム量は410mgで、野菜の中では比較的多い方です。自宅でじゃがいもを育てることで、高血圧のリスクを軽減する一助となるでしょう。
じゃがいもの美味しい食べ方
じゃがいもは、その水分豊富でやわらかく、香り高い特徴から、調理において様々な楽しみ方ができます。また、薄い皮を持つため、しっかり洗えば皮ごと調理することができます。通常のじゃがいもと比べて早く火が通るので、忙しい日常でも簡単に美味しい料理を楽しむことができます。ここでは、じゃがいもの特徴を活かしたおすすめの食べ方を紹介します。
丸ごと茹でて味わう
じゃがいもは柔らかく、あっさりとした味わいが魅力です。皮付きのまま丸ごと茹でる場合、濃い味わいの料理と組み合わせてみましょう。おすすめは、バター、イカの塩辛、明太子などです。これらの具材を上に乗せるだけで、誰でも簡単に楽しむことができます。
千切りにして水にさらす
じゃがいもを千切りや細切りにして水にさらすと、シャキシャキとした歯ごたえを楽しむことができます。この切り方なら、生でも食べることができますが、さっと火を通して中華炒め、ナムル、サラダにしても美味しいです。シャキシャキ感が料理にアクセントを加えます。
潰して粘り気を引き出す
茹でたじゃがいもはよく冷ましてから潰すと、粘り気が出てとろりとした食感を楽しむことができます。これにめんつゆをかけてそのまま食べたり、ハンバーグ状に丸めて焼いたり、揚げたりするなど、さまざまなアレンジが可能です。じゃがいもを潰す度合いによって、歯ごたえも変わり、自分の好みに合わせて楽しむことができるのも特徴です。
2. じゃがいもの栽培方法
じゃがいもの栽培時期
じゃがいもの栽培スケジュールは下記のとおりです。
| 月 | 春植え | 秋植え |
|---|---|---|
| 2 | 植え付け | |
| 3 | 植え付け | |
| 4 | 芽かき | |
| 5 | 収穫 | |
| 6 | 収穫 | |
| 7 | ||
| 8 | 植え付け | |
| 9 | 芽かき | |
| 10 | ||
| 11 | 収穫 | |
| 12 | 収穫 |
種イモの選定
まずは、種イモ選びに関して説明します。

種イモの購入時期
種イモは、12月下旬ごろから販売が始まりますが、初心者の方は寒さによる種イモの腐敗を避けるために、暖かくなる3月以降に購入することをおすすめします。
初心者におすすめの品種
じゃがいもには「男爵薯(だんしゃくいも)」、「メークイン」、「キタアカリ」、「インカのめざめ」などさまざまな品種が存在しますが、初心者にとっては育てやすさに大きな差はありません。品種選びの際には、料理での使いやすさや食感の好みを考慮して、自分が好きな品種を選ぶことができます。
種イモの選び方
種イモを選ぶ際には、農林水産省の検査機関の検査に合格し、品質が保証されたものを選ぶことが大切です。スーパーなどで販売されている通常のじゃがいもではなく、合格証の付いた種イモを選ぶようにしましょう。また、初心者が成功しやすいポイントは、切らずにそのまま植えられるほど小さな種イモを選ぶことです。目安としては、1kg当たり約20個程度の種イモがおすすめです。
芽出し
じゃがいもを育てる際、育成の成功に向けて重要なステップの一つが「芽出し」です。芽出しは、植え付けの2~3週間前から行う作業で、そのポイントをご紹介します。

芽出しのポイント1:日光に当てる
毎日、朝から夕方くらいまで、日なたに種イモを並べます。太陽光を浴びさせることが大切です。
芽出しのポイント2:夜間は取り込む
夜間は寒冷となるため、種イモを屋内に取り込みましょう。
芽出しのポイント3:芽出しの目標
通常、約2週間の間に、種イモから緑、赤、紫色の硬い芽が出てくることを目指します。
芽出しのポイント4:芽出しの利点
芽出しは必ずしも行う必要はありませんが、行うことで以下の利点があります。
発芽が均等になる
芽出しを行うことで、植え付け時にじゃがいもの発芽が均等になります。これにより、収穫時に一様なサイズのじゃがいもを得ることができます。
生育の促進
種イモの切り方
芽出しを行うことで、じゃがいもの成長を促進させることができます。より早く、健康的に成長することが期待できます。
じゃがいもを育てる際に、種イモを切る作業は大切なステップです。ここでは、種イモの切り方と植え付けにおけるポイントを詳しく説明します。
小さい種イモ(約30~50g)の場合
このサイズの種イモは切らずにそのまま植え付けます。切る必要はありません。
大きな種イモ(約50g以上)の場合
大きな種イモは、芽出しを行った後、大きさに応じて切ります。切り方は以下の通りです。
着るときのポイント
芽を残す
種イモには芽が出ている場所があります。この芽を残すように切ります。
均等な大きさにする
切った種イモは、1片が平均約40g程度になるように切ります。均一な大きさにすることが大切です。
植え付け
じゃがいもの育成において、種イモの植え付けは重要なステップです。以下に、種イモの植え付け方法と成功に向けたポイントを紹介します。
植え付け場所
種イモを植え付ける場所は、水はけの良い土壌が適しています。水が溜まらないように、排水の良い場所を選びましょう。
植え溝の掘り方
植え溝の幅
幅は約60〜70cm程度に設定します。この間隔は、じゃがいもが成長するために必要なスペースを確保します。
植え溝の深さ
植え溝の深さは約10cm程度が適しています。深すぎると、じゃがいもの芽が出にくくなる可能性があるため、注意が必要です。
植え付け間隔
種イモ同士の間隔は約30cm程度空けて植えると、じゃがいもの成長に適したスペースを確保できます。過密に植えないようにしましょう。
植え溝の土の上げ方
種イモは通常、土が上にのるくらいの深さが目安です。植え溝に土を掛けることで、適切な深さに植え付けることができます。
芽かき
芽かきは、じゃがいもの茎と葉を健康的に保ち、収穫量を増加させる重要な作業です。じゃがいもの葉は光合成を行い、栄養を供給します。茎と葉が地下に埋まることで、じゃがいもが地中で育ちやすくなり、収穫量が向上します。また、芽かきによって太陽光にさらされたじゃがいもが緑色に変わり、有害なソラニンの生成が防止されます。これにより、食中毒のリスクが軽減され、じゃがいもの品質も向上します。芽かきは、健康な成長と美味しい収穫を得るために不可欠なステップです。ここからは、芽かきの具体的なやり方について説明します。
芽かきのタイミング
じゃがいもから出てきた芽が約5cmほどに伸びたら、芽かきを行います。この時、硬くて健康そうな芽を数本残し、余分な芽を引き抜きます。
芽かきの方法
芽かきの本数
通常、2〜3本の芽を残すのが良いとされていますが、好みに応じて残す本数を調整することができます。
種イモの固定
種イモが動かないようにしっかりと押さえ、芽を切る作業を行います。
芽の切り方
土の下の方で芽を切るようにしましょう。芽をできるだけ近くで切ることが大切です。
土寄せ
土寄せは、じゃがいもの栽培において、茎と葉を地下に埋めて健康的な成長を促し、収穫量と品質を向上させる作業です。じゃがいもの茎が地中に埋まることで、茎の節から新たなじゃがいもが形成され、収穫時に多くの大きなイモを得ることができます。また、土寄せによってじゃがいもの茎や葉が地中に隠れ、外傷や傷つきを軽減し、品質を向上させます。さらに、茎や葉が地上に出ることで太陽光にさらされ、緑色に変わるリスクが減少し、有害なソラニンの生成を防止します。したがって、土寄せはじゃがいもの成長を管理し、収穫時に美味しさと安全性を確保する不可欠な作業です。ここからは、土寄せの具体的な方法について解説します。
1回目の土寄せ
芽かきが終わった後、軽く土寄せを行います。芽かきの際に土が低くなってしまった箇所を埋め、じゃがいもをしっかりと支えます。土寄せを行う際には、じゃがいもの茎部分を覆う程度の深さに土を寄せます。茎が光に当たらないように注意しましょう。
じゃがいもの栽培では、草丈が約30cmに成長した際に2回目の土寄せと追肥が必要です。以下に、このステップの方法と重要性を説明します。
2回目の土寄せ
草丈が約30cmほどに成長したら、2回目の土寄せを行います。この時点でじゃがいもが地上に露出している可能性があるため、土寄せが必要です。1回目と同様に、土に追肥を混ぜた後に土寄せを行います。じゃがいもが土から出てしまう箇所を埋め、茎を覆います。
追肥
追肥の方法
追肥を混ぜる前に、追肥材料をよく混ぜて均一な肥料を作ります。追肥を混ぜた後、じゃがいもの周りに均等に撒きます。追肥に含まれる栄養素がじゃがいもの成長を助けます。
追肥の役割1:栄養供給
追肥はじゃがいもに追加の栄養を供給し、健康な成長を促進します。特に成長が著しくなる時期に追肥を施すことで、収穫量や品質を向上させることができます。
追肥の役割2:ソラニンの防止
じゃがいもが太陽光に当たると、緑色に変わり、有害物質であるソラニンの含有量が増加する可能性があります。土から出たじゃがいもは土寄せして埋め、ソラニンの生成を防ぐ役割があります。
花摘み
じゃがいもの栽培において、花の取り扱いについて注意が必要です。花が咲くと、実が形成されることがありますが、これがじゃがいもの成長に影響を及ぼす要因の一つです。
花がじゃがいもの実に与える影響
栄養の競合
花が実をつけると、じゃがいもの成長に必要な栄養分が実の方に取られる可能性があります。これが収穫時のイモのサイズや品質に影響を与えることがあります。
エネルギー消費
花や実をつけるためにじゃがいもの植物はエネルギーを消費します。このエネルギーが茎や葉、地下の塊茎の成長に取られることで、収穫時の収量が減少することがあります。
花の摘み方
花が咲いた場合、できるだけ早く取り除くことをおすすめします。これによって、植物のエネルギーと栄養分が茎や塊茎に集中し、健康なじゃがいもの成長を促進します。ただし、花を取り除く際は、植物を傷つけないように注意深く行うことが大切です。

収穫
じゃがいもの収穫は栽培の最終ステップであり、品質を確保するために注意が必要です。以下に、収穫から取り扱いに至るポイントを説明します。

収穫のタイミング
収穫時期は一般的に6月中旬ごろですが、品種や地域、天候によって異なります。収穫の目安は、葉の7~8割が黄色くなり、枯れ始めた時です。雨天や雨上がりには収穫しないようにし、晴天で土が乾いている状態で行います。
収穫の手順
掘り上げる
じゃがいもは丁寧に掘り上げます。土が付着しても構いませんが、傷つけないように注意が必要です。
乾燥させる
掘り上げたじゃがいもは風通しの良い場所で土がさらっと落ちるまで乾燥させます。ただし、長時間日に当てると水分が過度に減少し、じゃがいもがシワシワになる恐れがあるため、注意が必要です。また、ソラニンの含有量も増える可能性があるため、適切な乾燥時間を守りましょう。
3. じゃがいも栽培によくあるトラブルと対策方法
これからじゃがいもを栽培する方や、じゃがいもの栽培のトラブルを解決しようとしている方は、栽培で発生するトラブルについて正しく理解する必要があります。ここからは、じゃがいもの主要な病気について、病気の症状とそれに対処する方法について詳しく説明します。
じゃがいもは様々な病害に対して感受性が高く、これらの病害が発症すると収穫量や品質に影響を及ぼす可能性があります。以下に、主要なじゃがいもの病害とそれに対する具体的な対策方法を詳しく説明します。
そうか病
病状
そうか病はストレプトマイセス属の放線菌により、じゃがいもの塊茎にコルク化した病斑が現れます。これは食味には影響しませんが、見た目が悪化し、商品価値が低下します。
対策方法
種イモの選別
消毒した種イモを使用し、合格証の付いたものを選びます。
連作を避ける
同じ場所でのじゃがいもの継続的な栽培を避け、輪作を行います。
感染した植物の早期除去: 感染したじゃがいもの早期発見と取り除き、感染拡大を防ぎます。
乾腐病
病状
乾腐病はフザリウム属菌により、じゃがいもの塊茎内部が褐変する症状が見られます。これは塊茎の品質を低下させます。
対策方法
消毒した種イモの使用
消毒した種イモを選びます。
連作を避ける
同じ場所での連作を避け、輪作を行います。
植物に傷をつけない
収穫時に植物に傷をつけず、感染の拡大を防ぎます。
軟腐病
病状
軟腐病はカビにより、塊茎や地下部から腐敗が始まり、強い臭いを放つ水浸状の病斑が現れます。
対策方法
土壌の改良
良好な水はけを確保するために、土壌の改良を行います。
収穫後の乾燥
収穫後は風通しの良い場所で日光に当てて乾燥させます。
殺菌剤や生物的防除剤
必要に応じて農薬を利用し、軟腐病の発病を防ぎます。
モザイク病
病状
モザイク病はウイルスにより引き起こされ、葉に斑点状の模様が現れます。
対策方法
アブラムシの飛来防止
マルチやトンネルを利用して、ウイルスを媒介するアブラムシの飛来を防ぎます。
感染した葉の除去
感染した葉を早期に除去し、感染の広がりを防ぎます。
青枯病
病状
青枯病は葉が青々としたまま株の一部が萎れる病気で、茎の断面に乳白色の菌泥が見られます。
対策方法
早期の株を除去する
感染した株は早めに引き抜いて処分し、感染の広がりを防ぎます。
連作の避ける
連作を避け、同じ場所での栽培を控えます。
4. まとめ
美味しいじゃがいもを育てるためには、正しい栽培方法や病害への対策方法の知識が必要です。また、じゃがいもの栄養素や美味しい調理方法を知ることで、じゃがいもを活かした消費者に喜ばれるビジネスのアイデアを生み出すきっかけになるかもしれません。じゃがいも栽培を通じて、より素晴らしい食生活を育みましょう。

- この記事の監修者