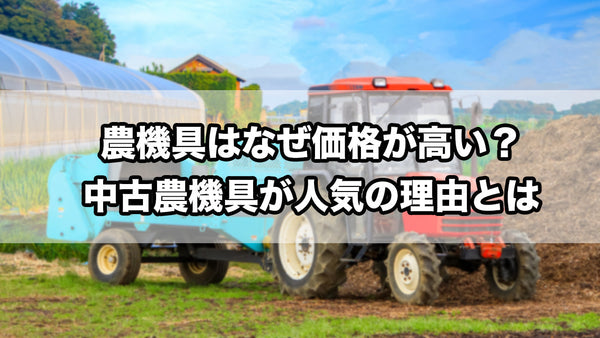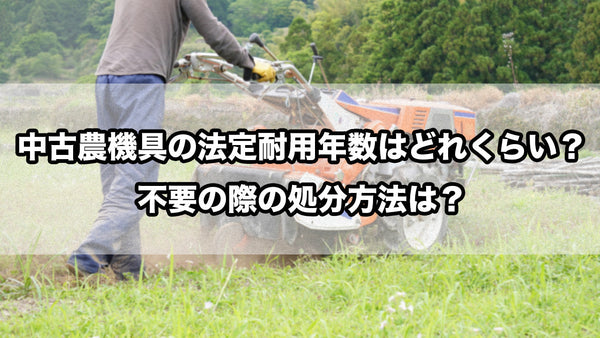建設現場や土木工事において欠かせない重機である、バックホー・ユンボ・パワーショベル。よく混同されがちな重機たちですが、実はそれぞれの機械が持つ特徴や役割は異なり、用途によって使い分ける必要があります。
これら重機の違いを理解することで、現場での作業を効率よく進めることができるでしょう。また、これらの重機を操作するには、特定の資格や免許が必要となる場合があります。一体、どんな資格が必要なのでしょうか?
この記事では、バックホー・ユンボ・パワーショベルの違いや、必要になる資格・免許などについて詳しく解説していきます。最後まで読むことで、これら重機の違いと、必要な資格についてしっかりと把握することができるはずです。
- [目次]
バックホー・ユンボ・パワーショベルの違い

建設現場や土木工事で頻繁に使用される「油圧ショベル」には、バックホー・ユンボ・パワーショベルなど、さまざまな呼び名が存在します。
この呼び名は地域や業界、さらには重機の使用用途によって使い分けれることが多いため、初めて接する方は混乱を招くことも少なくありません。
それぞれの呼び名が指す重機の特徴や背景を理解することで、適切な使用や効率的な作業が可能となるでしょう。以下では、これら重機の違いについて詳しく解説します。
バックホー
バックホーは、英語の「Backhoe」に由来し、「Back(後ろ)」と「Hoe(くわ)」を組みわせた言葉です。オペレーターから見て、バケット(掘削部分)が自分の方に引き寄せるように動作することから名付けられました。
バックホーはこの動作から、地表面よりも下の土を掘削する作業に適しています。日本においては、行政文書や土木・建設業界での正式な名称として「バックホウ」や「ドラグショベル」とも呼ばれているようです。
一般的な油圧ショベルの多くは、このバックホーの形式を採用しており、道路工事や建物の基礎工事など、さまざまな現場で活躍しています。その汎用性の高さから、建設業界では欠かせない存在となっています。
ユンボ
ユンボという呼び名は、もともとフランスの建設機械メーカーであるシカム社(SICAM)の製品名に由来します。
日本では、シカム社と技術提携を行った新三菱重工(現・三菱重工業)が、1961年に油圧ショベル「Y35」を「ユンボ」の愛称で発売しました。この製品が高い評価を受けたことで、「ユンボ」という名称が日本国内で油圧ショベルを指す呼称として広まりました。
現在では、建機レンタル企業「レンタルのニッケン」の登録商標となっていますが、地域や業界によっては「ユンボ」が油圧ショベルの代名詞として親しまれており、その呼び名は多くの人々に浸透しています。
パワーショベル
パワーショベルは、もともとコマツ(小松製作所)が自社の油圧ショベルに付けた商品名です。しかし、その名称が一般にも広く浸透し、現在では油圧ショベルを指す呼称として使用されています。
特徴としては、バケットがオペレーターから見て外向きに取り付けられたタイプの油圧ショベルを指す場合に「パワーショベル」という名称が用いられることが多いです。このパワーショベルは、車体より上部の土砂や資材の掘削・積み込み作業に適しており、大規模な土木工事や鉱山作業などで活躍しています。
一方で、一般的な油圧ショベルは、バックホー形式が主流であるため、現場で「パワーショベル」という名称が使われる際には、その仕様や用途に注意が必要です。
[おすすめ記事]
→農機具用バッテリーと自動車用バッテリーの違いは?
バックホーを運転するために必要な資格や免許は?

バックホーを運転するには、機体の重量や公道での走行の有無に応じて、適切な免許や資格を取得する必要があります。
まず、公道を走行する際には、車両の総重量と最大積載量に応じた自動車運転免許が必要です。運転するバックホーが、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2.0トン未満の場合は「普通自動車免許」が必要となります。
ただし、クローラ式のバックホーは公道を走行できないため、ホイール式のバックホーを運転する際にのみ該当します。
次に、機体重量が3トン未満のバックホーを操作する場合は「小型車両系建設機械の運転の業務に係る特別教育」を修了する必要があります。この特別教育は、学科7時間と実技6時間の計13時間で構成されており、費用は約2万円です。
機体重量が3トン以上のバックホーを操作する場合は、「車両系建設機械運転技能講習」を修了し、試験に合格する必要があります。この講習は、学科13時間と実技25時間の計38時間で構成されており、費用は約5万円です。
[合わせて読みたい記事]
→電動チェンソーの使用は資格は必要?取得は難しい?
バックホーの代表的な機種は?

バックホーは、建設現場で土砂の掘削や積み込みなどに使用される、作業に欠かせない重機です。各メーカーから多様な機種が提供されていますが、その中でも特に注目される代表的なモデルをご紹介します。
1. コマツ「PC40MR-3」
コマツの「PC40MR-3」は、建設業界でシェア率1位を誇る人気機種です。
4トンクラスのミニ油圧ショベルで、狭い現場でも高い作業効率を発揮する後方小旋回機能が特徴です。最新の環境基準に適合したエンジンを搭載し、燃費性能と排出ガスの低減を実現しています。
操作性と快適性を追求したキャブデザインや、メンテナンス性の向上を図った設計も施されており、耐久性の高い構造と先進の油圧システムにより、多様な作業に対応可能です。
2. 日立「ZX30U-5B」
日立の「ZX30U-5B」は、3トンクラスの後方超小旋回型ミニショベルとして設計されています。電子制御式エンジンや効率的な油圧システムを採用し、低燃費と高い作業性能を両立しています。
「オートアイドル機能」や「オートアイドリングストップ機能」を搭載し、環境負荷の軽減にも配慮しており、PWRモードとECOモードの2つの作業モードを備え、作業内容に応じた最適な運転が可能です。また、3.6インチの大型マルチ液晶モニタを採用しているため、視認性と操作性が向上します。
3. ヤンマー「VIO20」
ヤンマーの「VIO20」は、2トンクラスのミニショベルで、後方超小旋回機能を持つモデルです。機械質量は1,990kg、バケット容量は0.06m³で、狭い現場での作業に適しています。「オートデセル・エコモード」を搭載し、無負荷時のエンジン自動減速機能により、燃費性能を向上させています。
また、油圧式クイックヒッチ(オプション)により、工具を使わずにバケット交換が可能で、作業効率を高めています。さらに、スマートアシストリモートを装備し、機械の稼働管理や盗難防止に役立てることができます。
4. クボタ「KX038-4e」
クボタの「KX038-4e」は、電動ミニバックホーで、都市部での作業や環境に配慮した現場に最適なモデルです。機械質量は3,870kg、モーター出力は17.8kWで、都市部の配管工事や掘削工事など、幅広い用途に対応します。
この電動ミニバックホーは、従来のディーゼルエンジン搭載機と比較して、圧倒的な静音性とゼロエミッションを実現しています。これにより、騒音や排ガスが気になる都市部や、環境規制の厳しい現場でも、安心して作業を行うことができます。
また、日本の急速充電規格である「チャデモ」に対応しており、120分の急速充電で4時間以上の稼働が可能です。これにより、充電時間を気にすることなく、効率的に作業を進めることができます。
さらに、クボタの長年培ってきた建設機械の技術とノウハウが活かされており、高い耐久性と操作性を兼ね備えています。これにより、過酷な現場環境でも、安定した性能を発揮し、作業効率の向上に貢献します。
「KX038-4e」は、環境性能と作業効率を両立した次世代のミニバックホーです。
まとめ
今回は、バックホー・ユンボ・パワーショベルの違いや、必要になる資格・免許などについて解説してきました。
建設現場で使用される油圧ショベルには、「バックホー」「ユンボ」「パワーショベル」などの呼び名があり、それぞれ由来や用途が異なります。
「バックホー」は、バケットがオペレーター側に引き寄せる動作をするのが特徴です。「ユンボ」は、フランスのメーカーの製品名が由来となっています。「パワーショベル」は、コマツが自社製品に使用した名称で、大規模な土木工事に適したタイプを指すことが多いです。
バックホーを運転するには、機体重量に応じた資格や免許が必要です。3トン未満なら特別教育、3トン以上なら技能講習を受講する必要があります。公道を走行する場合は、普通自動車免許も必要になるでしょう。