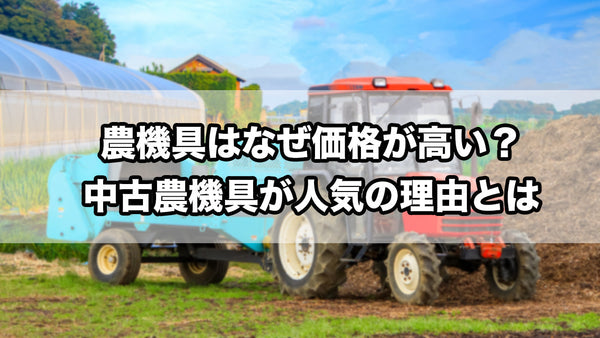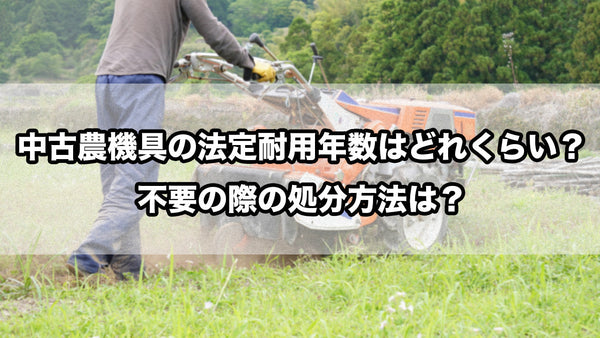新鮮な野菜を育てるためには、正しい栽培方法と病気への対策が欠かせません。特に、キュウリの栽培において、適切な土づくりから始まり、収穫までの工程を理解することが成功の鍵です。この記事では、キュウリの栽培に関する重要なポイントや、病気の防除方法について詳しく紹介します。
1. キュウリの特徴
キュウリを栽培する農家にとって、栄養素や調理方法の理解は極めて重要です。まず、栄養素の知識は収穫物の品質向上に直結し、市場価値を高める要因となります。また、消費者が健康を意識する現代社会において、キュウリが提供するビタミンやミネラルなどの栄養価は貴重です。調理方法の理解は、キュウリをより美味しく楽しむために欠かせず、多彩な料理への活用が可能です。栽培から調理までの一貫した知識が、農家の生産性向上と市場競争力の強化につながり、顧客満足度を向上させるでしょう。したがって、農家は栽培技術だけでなく、キュウリの栄養価と調理法にも注力すべきです。ここからは、キュウリの栄養素とおすすめの調理方法について解説します。
栄養素
キュウリは、さまざまな栄養成分が豊富に含まれており、その健康への効果は見逃せません。ここからは、キュウリに含まれる主要な栄養成分とその効能について詳しく解説します。
カリウム
キュウリにはカリウムが多く含まれています。カリウムは体内で重要な役割を果たすミネラルであり、特に血圧の調整に役立ちます。血圧を安定させることは、心臓血管系の健康を維持するために非常に重要です。カリウムは水溶性ですので、キュウリを生で食べることで効率的に摂取できます。茹でたり煮たりすると、カリウムが水に溶け出してしまうので注意が必要です。
ビタミンC
キュウリにはビタミンCも多く含まれています。ビタミンCは免疫力を高め、皮膚を健康に保つために必要な栄養素です。また、ビタミンCには抗酸化作用もあり、紫外線から肌を守る助けになります。さらに、動脈硬化の予防や老化の遅延にも寄与すると言われています。ビタミンCは熱に弱いため、キュウリを生で摂取することが最も効果的です。
食物繊維
キュウリは食物繊維も豊富に含んでいます。食物繊維は脂質、糖、ナトリウムなどを吸着し、体外に排出する役割を果たします。これにより、肥満、脂質異常症、糖尿病、高血圧などの生活習慣病の予防や改善が期待できます。また、腸内環境を整え、便秘の解消にも寄与します。健康を考える上で、食物繊維を意識的に摂取することは非常に重要です。
β-カロテン
キュウリに含まれるβ-カロテンは、体内でビタミンAに変換されます。これは目の健康をサポートし、特に夜間や薄暗い場所で視力を維持するのに役立ちます。また、β-カロテンには日焼けやシミの予防にも効果があるとされています。キュウリを食事に取り入れることで、これらの健康効果を享受できるでしょう。
キュウリの美味しい食べ方
生のキュウリは、そのまま食べるというシンプルながらも爽やかで美味しい食材です。ここからは、人気のある生のキュウリの食べ方と、その栄養効果について詳しくご紹介します。
丸かじり
生のキュウリをそのまま食べる場合、最もポピュラーな食べ方は、まるごと1本のキュウリを丸かじりすることです。この食べ方は、キュウリの特有の歯ごたえとみずみずしさを最大限に楽しむ方法として愛されています。新鮮なキュウリであれば、何もつけずにそのまま丸かじりしても美味しいですが、塩や味噌、マヨネーズをつけて丸かじりすることも多いです。また、生のキュウリをおいしく食べるには、下記の調理工程が重要です。
板ずり
生のキュウリを食べる際、下ごしらえとして「板ずり」を行うと、より美味しく楽しむことができます。板ずりは、キュウリの両端を少し切り落とし、塩をふったまな板の上にキュウリを置いてコロコロと転がす方法です。これにより、キュウリの青みやイボを取り除き、食感を向上させます。
切り方
切り方にも工夫があります。輪切りにすると、噛みやすくなりますし、千切りにすると歯ごたえを楽しむことができます。
キュウリサラダ
また、サラダとして食べるのも定番中の定番の食べ方です。サラダにする際、他の食材と組み合わせることで、さまざまなサラダのバリエーションを楽しむことができます。和え物や酢の物にする方法も、人気があります。これらの食べ方は、食材を組み合わせることでバリエーションを広げるのに適しています。
冷や汁にする
キュウリを主役にした冷や汁は、宮崎県の郷土料理としても知られています。豆腐やあじの干物などを加えることで、汁物と主菜を一緒に楽しむことができます。冷や汁はごはんにかけて食べるのが一般的な食べ方です。
豚肉を巻いて焼く
キュウリは加熱しても美味しい食材です。縦に薄く切ったキュウリを豚肉で巻き、フライパンで焼くだけで簡単に作れます。ベーコンを使っても良いでしょう。味付けは塩コショウや焼き肉のたれを絡めるなど、自分の好みに合わせて調理してみてください。
卵やエビと一緒に炒める
フライパンにごま油を加え、キュウリの薄切りとむきえび(冷凍)を加え、溶き卵と塩コショウで調味すると、美味しい一品が完成します。塩コショウの代わりに醤油や砂糖、酢を使って甘酢仕立てにすることもおすすめです。
2. キュウリの栽培方法
キュウリの栽培時期
キュウリの栽培スケジュールは下記のとおりです。
| 月 | 一般的なキュウリ | 夏植えキュウリ |
|---|---|---|
| 3 | 土づくり | |
| 4 | 植え付け | |
| 5 | 植え付け | 土づくり |
| 6 | 収穫 | 植え付け・収穫 |
| 7 | 収穫 | 植え付け・収穫 |
| 8 | 収穫 | 収穫 |
| 9 | 収穫 |

土づくり
キュウリを美味しく育てるためには、適切な土づくりが欠かせません。ここからは、キュウリの栽培における土づくりのポイントを詳しくご紹介します。
適切な場所
まず、キュウリの栽培に適した場所を選びましょう。キュウリは日当たりが良い場所を好みますので、できるだけ直射日光の当たる場所を選びます。また、連作障害を防ぐために、前回キュウリを植えた場所ではなく、異なる場所を選ぶようにしましょう。
土づくりの手順
土づくりは、植え付けの2〜3週間前に始めます。また、1週間前には肥料を加え、畝を作ります。詳細な手順は下記を参考にしてください。
土の成分比
土は、堆肥を2kg/㎡、苦土石灰を150g/㎡という割合で用意します。これらを土に混ぜ込み、良く耕して土づくりを行います。堆肥は土を肥えさせ、苦土石灰は土壌のpHを調整するのに役立ちます。良い土壌状態を整えるために、しっかりと耕してください。
配合肥料の混入
配合肥料(例:8 - 8 - 8)などを100g/㎡の割合で用意し、土に混ぜ込みます。これにより、キュウリに必要な栄養分を土壌に供給します。配合肥料の選択に注意し、キュウリの栄養要求を満たすものを選びましょう。
畝を作る
幅約60cm、高さ約20cmの畝を作ります。畝は水はけが良く、根の発育を促進するために必要です。
マルチを張る
畝の上にマルチを張りましょう。マルチは雑草の侵入を防ぎ、土を温め、水分を保持する役割があります。また、キュウリの実を清潔に保つ効果もあります。マルチを張ることで、キュウリの病気にかかりにくくなります。
キュウリの植え付け
キュウリは美味しい夏野菜の一つですが、適切な栽培条件を整えることが成功の鍵です。ここからは、キュウリの栽培におけるポイントを詳しく解説します。
適切な気候と寒さ対策
キュウリは暖かい気候を好む作物ですが、4月上中旬のまだ寒冷な時期には注意が必要です。寒さに弱いため、霜や寒波から守るために防風・防寒対策が必要です。寒冷な日が続く場合、プラスチックフィルムや農業用のカバーを使用するなどの対策を行いましょう。
仮支柱の設置
キュウリの茎は細く、葉が大きいため、風の抵抗を受けやすいです。定植直後には必ず「仮支柱」を立てましょう。仮支柱は、茎が折れないようにするために重要です。

適切な株間と支柱の設置
畑でのキュウリの栽培の場合、株間を広めにとることが重要です。株間を50cm以上確保することで、キュウリの健康な成長を促進します。また、キュウリが大きく生長し、高さが2mに達するときには、しっかりとした支柱を立てましょう。
支柱を立てたら、伸びてくる「つる」がからみやすいよう、紐やネットを張って準備しておきます。キュウリのつるは成長が早いため、1週間に1度は支柱などに麻紐で誘引して茎葉が折れないようにしましょう。
追肥
キュウリを美味しく育てるためには、追肥(追加の肥料施用)が欠かせません。ここからは、キュウリの追肥についてのポイントを詳しく解説します。
配合肥料の使用
草勢を見ながら、2週間に1回を目安に配合肥料を約30g/㎡を施すことをお勧めします。追肥には、キュウリに必要な栄養素を供給する役割があります。配合肥料はキュウリの成長に合わせて追加することで、株の勢いを保つのに役立ちます。
夏場の追肥
キュウリは夏場に生長が早くなるため、毎日の水やりに加えて、薄い液肥を使用することも検討されます。薄い液肥は水に溶かして使うことができ、キュウリに必要な栄養分を迅速に供給します。夏場の追肥はキュウリの健康な成長を促進するために重要です。
配合肥料のすき込み
畝の両側に1株あたり、配合肥料を約50gずつすき込みます。ただし、キュウリの根は浅いため、根を傷つけないように注意が必要です。配合肥料を土に混ぜ込む際に、軽く耕すなどして均一に分散させましょう。
整枝
キュウリの栽培において、整枝は収穫量や品質を向上させる重要な要素です。ここからは、キュウリの整枝方法と、栽培タイプ別のアドバイスを紹介します。
整枝の基本ポイント
整枝は、キュウリの茎や葉を適切に整え、健康的な成長と実りを促す作業です。以下は、整枝の基本ポイントです。
主枝と側枝のバランスを保つ
側枝が過剰に成長するのを防ぐため、主枝を伸ばし、株全体のバランスを取ります。側枝は株元から5〜6節までに出てくるものを摘み取ります。
摘心
子づるが伸びてくる際に、2〜3枚の葉を残して摘心します。これにより、着果が促進され、実りが豊かになります。
老化葉の剪定
収穫が進んだ生育中盤以降、株元に近い老化した葉を順に摘み取ります。これにより、株全体の健康を維持し、実りが良くなります。
品種別の整枝方法
主なキュウリの品種ごとの整枝方法を説明します。
強健豊作
主枝と子づる、孫づるにバランスよく着果するタイプ。株元から5〜6節までに出てくる側枝を摘み取り、以降は無整枝で育てます。
スティックミニ
主枝と子づるにバランスよく着果するタイプ。株元から5〜6節までに出てくる側枝を摘み取り、その後に伸びてくる子づるは2〜3枚の葉を残して摘芯します。
バリうま
節成り性が高いタイプ。基本的に主枝に雌花がつきやすいため、側枝は摘み取り、1本仕立てとします。
コクうま
主枝と子づるにバランスよく着果するタイプ。株元から5〜6節までに出てくる側枝を摘み取り、その後に伸びてくる子づるは2〜3枚の葉を残して摘芯します。
夏ふうみ
主枝と子づる、孫づるにバランスよく着果するタイプ。整枝は基本的に不要で、多くの側枝を維持して栽培します。
ポリッキュ
節成りタイプで、主枝の各節に雌花が多数着生する品種。側枝は摘み取り、1本仕立てとします。生育中に株が弱ってきた場合は、子づるを摘芯せず伸長させることができます。
水やり
キュウリは水分を大切にする作物であり、適切な水やりは健康な成長と豊かな実りに不可欠です。キュウリの水やりに関するコツと注意点を以下に解説します。
乾燥に弱い作物
キュウリは乾燥に非常に敏感な作物です。特に夏場やコンテナ栽培では、乾燥しやすいため、こまめな水やりが必要です。乾燥に対する注意が必要な時期や条件を以下に示します。
夏場の水やり
夏季は特に乾燥が激しいため、毎日水やりを行いましょう。ただし、炎天下の日中は避け、朝か夕方、気温が下がってからたっぷりと水を与えます。
根張りの浅さ
キュウリの根は浅いため、土壌に有機物を多く含む堆肥などを使用して根の張りを良くしましょう。根がしっかりと張ることで、水分の吸収能力が向上します。
水を惜しまない
キュウリは「水で育てる」と言われるほど、水分を多く必要とします。水分が不足すると成長に支障をきたし、実りが減少します。以下は水やりに関する注意点です。
水切れは厳禁
肥料が切れることはもちろんですが、水切れも絶対に避けましょう。特にプランター栽培など、乾燥しやすい環境では、水切れに特に注意が必要です。
水分吸収の増加
キュウリが大きく成長すると、1株で1日に約1.5リットルの水分を吸収すると言われています。このことから、成長段階に応じて十分な水分を供給する必要があります。
収穫
キュウリを美味しく収穫するためには、収穫のポイントと適切なタイミングを知ることが重要です。ここからは、キュウリの収穫に関するコツを詳しく紹介します。
若い果実の収穫がポイント
キュウリを収穫する際のポイントの一つは、若い果実の収穫です。最初と2番目につく実は特に若穫りしましょう。なぜなら、若いキュウリは味が良く、株の消耗を防ぐためでもあります。以降の収穫は、品種によっておいしいタイミングが異なるため、それぞれの収穫適期サイズを見逃さないように注意が必要です。
特に夏場は、開花から1週間ほどで収穫可能になり、朝と夕方で大きさが変わるほどの速さで成長します。放っておくと、成熟果になってしまいますが、これを種を取り除いて漬物にすることも可能です。

品種ごとの収穫適期サイズ
各品種ごとに収穫適期サイズが異なります。以下は一般的なキュウリ品種とその収穫適期サイズの一覧です。
- スティックミニ: 12~15cm
- バリうま: 25~35cm
- 強健豊作: 21~22cm
- 夏ふうみ: 21~22cm
- コクうま: 20~22cm
- ポリッキュ: 6~8cm
収穫適期サイズを守ることで、キュウリの食感や味わいを最大限に楽しむことができます。収穫の際は、果実を丁寧に切り取り、きれいな形で収穫しましょう。
3. キュウリ栽培によくあるトラブルと対策方法
これからキュウリを栽培する方や、キュウリの栽培のトラブルを解決しようとしている方は、栽培で発生するトラブルについて正しく理解する必要があります。ここからは、キュウリの主要な病気について、病気の症状とそれに対処する方法について詳しく説明します。
べと病
キュウリのべと病は、栽培中に起こりやすい病気の一つです。ここからは、べと病の症状、診断方法、そして効果的な対策方法について詳しく説明します。
べと病の症状
べと病の症状は以下のように現れます。
葉だけが侵される
べと病は通常、葉だけに症状が現れます。
子葉の初期症状
子葉では、最初に水浸状の斑点ができ、次第に拡大して淡褐色に変わり、薄くなります。乾燥すると少し萎凋します。
本葉の初期症状
本葉では、初めに淡黄色の小斑点ができ、やがて葉脈に囲まれて角張った黄褐色斑点になります。激発すると葉面全体が黄褐変し、水分を失って破れやすくなり、葉縁から巻き上がって枯れます。
湿度の高い条件下
湿度の高い条件下では、葉裏に紫黒色のかびが生えることもあります。
べと病の防ぎ方
べと病を防ぐためには、以下の対策を取ることが重要です。
茎葉の繁茂を避ける
キュウリの茎葉が密集しすぎないように注意しましょう。
十分な換気
ハウス栽培の場合、十分な換気を行い、湿度の低下を図ります。
初発からの防除
べと病は多発すると防除が難しくなるため、初発からの防除を徹底しましょう。
防除薬剤
べと病の防除には、以下の薬剤が使用されます。
- ゾーベックエニベル顆粒水和剤
- ピシロックフロアブル
- ライメイフロアブル
- ホライズンドライフロアブル
- ランマンフロアブル
- エトフィンフロアブル
- ザンプロDMフロアブル
- ベジセイバー
- リドミルゴールドMZ
- ジマンダイセン水和剤
- ダコニール1000
また、これらのほか有機JAS認定で使用できる薬剤として、クリーンカップとケミヘルがあります。
うどんこ病
うどんこ病は、植物の葉に発生する一般的な病気の一つで、特にキュウリなどの作物に被害を与えることがあります。ここからは、うどんこ病の症状、診断方法、および効果的な対策方法について詳しく説明します。
うどんこ病の症状
うどんこ病の症状は以下のように現れます。
葉に発生
うどんこ病は主に植物の葉に発生します。
下位葉から発生
発病は通常、下位葉から始まります。
葉面に白いかびが発生
葉面には、うどん粉をまぶしたかのような白いかびが生えます。
植物体全体が覆われる
病勢が進行すると、植物体全体が汚白色のかびで覆われ、葉が黄化して枯れることもあります。
黒色の小粒(子のう殻)
病斑上に黒色の小粒(子のう殻)が生じることもあります。
うどんこ病の防ぎ方
うどんこ病を防ぐためには、以下の対策が重要です。
適切な植物の配置
過繁茂状態で植物を配置しないようにしましょう。
施設栽培での注意
施設栽培の場合、外張りビニールが汚れて日照が不足すると、うどんこ病の被害が増加することがあります。定期的にビニールを清掃し、日照を確保しましょう。
葉の裏側の観察
うどんこ病の初発については、葉の裏側にも注意して観察しましょう。
防除薬剤
うどんこ病の防除には、以下の薬剤が使用されます。
- パレード20フロアブル
- ネクスターフロアブル
- ベジセイバー
- アフェットフロアブル
- ケンジャフロアブル
- ラミック顆粒水和剤
- パンチョ顆粒水和剤
- ピカットフロアブル
- オルパ顆粒水和剤
- プロパティフロアブル
- ベルクートフロアブル
- ガッテン乳剤
- パルミノ
- サンヨール
- また、生物薬剤としては、以下のものがあります。
- セレナーデ水和剤
- タフパール
- インプレッション水和剤
- ボトキラー
さらに、有機JAS認定で使用できる薬剤も存在します。エコピタ液剤などがその一例です。
黒星病
黒星病は、植物の茎や果実に被害を及ぼす病気の一つで、特にキュウリなどの作物に影響を与えることがあります。ここからは、黒星病の症状、診断方法、および効果的な防除方法について詳しく説明します。
黒星病の症状
黒星病の症状は以下のように現れます。
茎の先端や未展開の幼葉、幼果に侵害
黒星病は茎の先端に近い部分や未展開の幼葉、幼果に侵害されやすいです。
斑点の形成
茎や果実に初めは暗緑色で円形ないし楕円形の水浸状の斑点が生じます。
斑点が褐変
次第にこれらの斑点は褐変し、へこんだ病斑となります。
黒褐色ビロード状のかび
病斑の表面には黒褐色ビロード状のかびが生えます。
裂けた病斑
病斑の中央部は裂け、ヤニを分泌することがあります。
茎の異常生育
細い茎が侵害されると、そこから先の生育が停止し、後にわき芽が叢生し、茎先端の異常な成長を呈することがあります。
湾曲した果実
果実は病変部を内側にして湾曲することがよくあります。
黒星病の防ぎ方
黒星病を防ぐためには、以下の対策が役立ちます。
湿度の管理
多湿な条件下では黒星病が発生しやすくなります。ハウス栽培の場合、換気を行って湿度を低く保つようにしましょう。
抵抗性のある品種を選ぶ
抵抗性のあるキュウリ品種を選ぶことで、黒星病の発生リスクを減らすことができます。
防除薬剤
黒星病の防除には、以下の薬剤が使用されます。
- アミスターオプティフロアブル
- トップジンM水和剤
- ワイドヒッター顆粒水和剤
- ピカットフロアブル
- ベジセイバー
- ダコニール1000
- スコア顆粒水和剤
- ファンベル顆粒水和剤
- ジマンダイセン水和剤
- トリフミン水和剤
- ベルクートフロアブル
発病初期からこれらの薬剤を散布することが、黒星病の効果的な防除に役立ちます。作物の健康を保つために、黒星病に対する適切な対策を実施しましょう。
4. まとめ
キュウリの栽培において、土づくりから水やり、整枝、収穫、そして病気の防除まで、さまざまな要因が収穫の品質に影響を与えます。土づくりには堆肥や肥料の適切な配合が必要であり、水やりには乾燥を防ぐ工夫が求められます。整枝方法には品種ごとの適した手法があり、収穫は適切なタイミングで行うことが重要です。
病気の防除は作物の健康を保つために不可欠であり、黒星病、べと病、うどんこ病などに対する対策も紹介しました。防除薬剤の使用や抵抗性の品種選定など、病気への対処法を理解することが、豊作な収穫を実現する鍵です。キュウリの栽培に挑戦する際には、これらのポイントを押さえて、美味しいキュウリを収穫しましょう。
- この記事の監修者