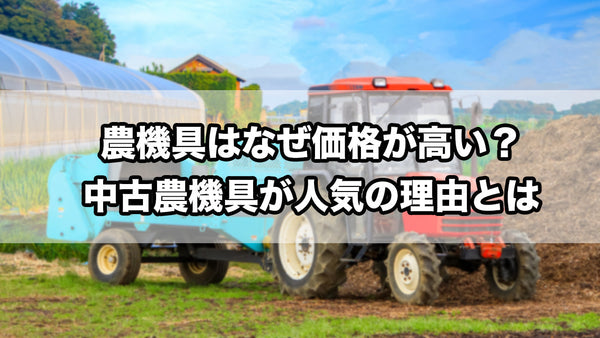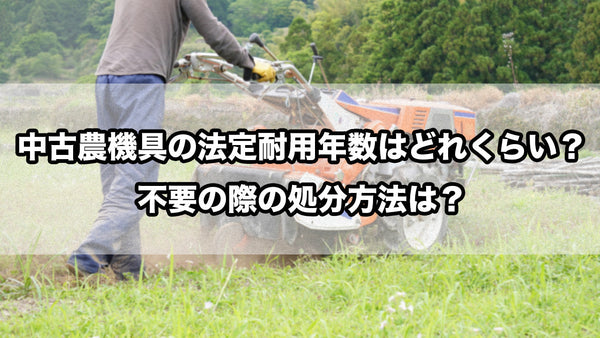稲や麦などの穀物を収穫する際に欠かせない農機具である「コンバイン」は、農作業の効率化に大きく貢献している機械です。
しかし、これから農業を始めようとしている方は「コンバインは農作業に欠かせない」と言われても、具体的に何ができる機械で、どう便利なのかよくわからない方も多いと思います。
また、コンバインには「自脱型」「汎用型」「普通型」という種類があり、収穫する作物や環境によって種類が異なります。それぞれに特徴や適した場面があり、選び方を間違えると作業効率や作物の質に影響を与えてしまう可能性もあります。
これら種類の違いを理解することで、あなたの農作業に最適なコンバインは何なのか知ることができるでしょう。
この記事では、農業において重要な役割を担うコンバインとは何なのか、
自脱型・汎用型・普通型の種類ごとの違いなどを徹底的に解説していきます。中古農機具やコンバインの導入を検討している方や、農業に興味がある方などに役立つ情報が満載ですので、ぜひ最後まで読んでみてください。
- [目次]
農業機械のコンバインとは?

コンバインとは、農作業の効率化を目的に、収穫・脱穀・選別の3つの機能を一体化した農業機械です。その名称は「Combine」(組み合わせる)に由来しており、刈取機と脱穀機を組み合わせた構造になっています。刈り取った穀物を瞬時に脱穀し、穀粒と茎や葉などの不要物を分離して、きれいな穀粒だけを選別する、という作業を連続して行うことができます。
コンバインが導入される以前は、これらの作業を全て手作業で行なっており、膨大な時間と労力を要していました。刈り取りには鎌を使い、脱穀には千歯扱きや唐箕という専用の道具が使われていましたが、コンバインの導入により、農作業にかかる時間は大幅に短縮され、生産性向上に大きく貢献しました。
日本にコンバインが導入されたのは、1950年代後半のことです。
欧米から大型のコンバインが輸入されましたが、当時の日本の水田は小さく足場も悪いため、うまく作業ができず、穀粒をたくさん無駄にしてしまう問題がありました。
そこで、日本の農家のために、日本独自のコンバインが開発されることになりました。それが後に解説する「自脱型コンバイン」になります。
このコンバインによって、小さい水田でも作業がしやすくなり、穀粒の損失も減らすことに成功しました。
コンバインの自脱型・汎用型・普通型それぞれの違いは?

コンバインは農作物の収穫に欠かせない機械であり、その種類によって収穫できる作物が異なります。主に「自脱型」「汎用型」「普通型」の3種類が存在し、それぞれ以下のような違いがあります。
・自脱型コンバイン
稲や麦など穀物の収穫に特化している。刈り取った穂先だけを脱穀・選別する機能を持つ。日本の水田に適している。
・汎用型コンバイン
複数の作物に対応可能。刈取部を交換することで大豆やトウモロコシなどの収穫もできる。
・普通型コンバイン
刈り取った作物全体を脱穀部に送り、作物だけを回収する。大型のため、日本の水田には不向き。
自脱型コンバインとは
自脱型コンバインは、収穫・脱穀・選別の作業を一台で行うことができ、主に稲や麦といった穀物の収穫に特化しています。自脱型コンバインの特徴は、刈り取った作物の穂先だけを脱穀部に取り込み、脱穀・選別を行うことです。茎は刈り株として残され、後に田んぼの肥料、あるいは家畜の飼料や堆肥として再利用されます。
自脱型コンバインは、日本の小さな水田でも作業しやすいように、小型で軽量な機種が多いです。また、穂先だけを取り込むので穀粒をあまり傷つけることなく選別ができ、高品質の収穫が可能になります。
しかし、大型の普通型コンバインと比較すると、一度に収穫できる量は少ないため大規模な畑作には不向きと言えます。また、刈取機と脱穀機を君合わせた構造は複雑なため、定期的な点検や部品交換が必要になり、メンテナンス費用が高額になる傾向にあります。
日本の農業環境に合わせて独自で開発された自脱型コンバインは、日本の稲作や麦作を支える重要な役割を担っており、必要不可欠な農機具と言えるでしょう。
[関連記事]
→米農家必見!生産者向けのお米の品種10選
汎用型コンバインとは
汎用型コンバインは、その名の通りさまざまな作物の収穫に対応できるように設計されたコンバインです。刈取部を交換することで、稲や麦だけでなく、大豆・とうもろこしなど、さまざまな作物を収穫できます。
このため、複数の作物を育てている農家は一台の汎用型コンバインで済むため、非常に経済的な選択肢となります。
しかし、汎用型コンバインは特定の作物に特化した自脱型や普通型などに比べると、それぞれの作物に対する収穫効率は若干劣る場合があります。また、刈取部を交換する手間や、それぞれの作物に合わせた調整が必要となるため、作業の手間が増えるという側面もあります。
普通型コンバインとは
普通型コンバインは、刈り取った作物全体を脱穀部に取り込み、脱穀・選別を行う方式です。主に欧米などの大規模農場で、麦や大豆、トウモロコシなどの収穫に用いられています。一度に大量の作物を収穫できるため、広大な農地での作業を効率的に行うことができ、最近ではGPSや無人自動運転など最新技術が搭載された機種も登場しており、作業効率はさらに向上しています。
また、自脱型コンバインとは異なり構造がシンプルなため、メンテナンスが行いやすく、耐久性も高いです。
しかし、普通型コンバインは大型で重量もあるため、日本の小さな水田での運転は向いていません。また、選別機能が自脱型ほど優秀ではないため、穀粒を無駄にしてしまいやすいです。さらに、刈り取った作物を全て取り込むため、茎や藁が細かく砕けてしまい、再利用が難しいというデメリットもあります。
これらのことから大規模な畑作を行う農家にとって、普通型コンバインは大幅に作業効率が上がるため、大きなメリットをもたらしていると言えます。
コンバインの構造はどうなってる?

コンバインは以下のような構造になっています。
1. 刈取部
作物を刈り取る役割を担います。刈取部は、作物の高さや密度に合わせて調整可能で、効率的に刈り取ることが可能です。
2. 搬送部
刈り取られた作物を脱穀部へと運ぶ部分です。搬送チェーンや掻き込みベルトが使用されて搬送されていきます。
3. 脱穀部
作物から穀粒を取り出す工程です。内部には「こぎ胴」と呼ばれる回転軸があり、歯が付いています。こぎ胴が回転することで、稲穂からモミをこぎ落とし、脱穀を行います。
4. 穀粒処理部
穀粒処理部には、選別されたモミを一時的に保管するタンクや、収穫袋に詰める機構が含まれています。
5. 排藁処理部
脱穀後に残った茎や藁を処理する部分です。細かく裁断して撒く「チョッパー」や、束ねて排出する機構が備わっています。これにより、次の耕作や土壌改良に役立てることができます。
これらの部分が連携して動作することでコンバインは、収穫・脱穀・選別、そして収穫物の保管までの一連の作業を効率的に行います。
コンバインを販売している大手メーカーのご紹介

日本の農業機械市場には多くのメーカーが存在しますが、特に代表的な4社である「井関農機(イセキ)」「クボタ」「三菱マヒンドラ農機」「ヤンマー」に焦点を当て、各社が販売しているコンバインの特徴をご紹介していきます。
各社は長年に渡り、農業の発展に貢献しており、農家のニーズに合わせてコンバインは進化し続けています。
井関農機(イセキ)
井関農機(イセキ)は、1966年に国内初の自脱型コンバイン「フロンティア」を発売した実績を持つ、日本の農業機械メーカーです。
イセキのコンバインは、特に稲作農家からの支持が厚く、日本の稲作を力強く支えています。業界で初めて7条刈りコンバインを開発するなど、常に技術革新の最前線に立ってきました。近年では、ICT技術を活用したスマート農業に対するコンバインの開発にも力を入れており、作業効率の向上やデータに基づいた精密な農業の実現に貢献しています。
このような技術開発への注力こそが、イセキが日本の農機具業界をリドする存在であることを示しています。日本国内のみならず、世界の農業機械市場においても重要な役割を担っているイセキは、これからも農業の発展に貢献していくことでしょう。
クボタ
クボタは、農機具の国内シェアでトップを誇るメーカーであり、世界的にも高い評価を受けています。
クボタのコンバインは、操作のしやすさを重視した設計が特徴で、高齢の農家からも高く評価されています。例えば、ボタンやレバー1つで刈り取りの準備が完了する機能や、刈り取り作業と同時に食味や収穫量を測定できる機能など、ユーザーにとって便利な機能開発に力を入れています。
2018年には、GPSを利用した自動運転アシスト機能「Agri Robo」を搭載したモデルなど、先進的な技術なども積極的に導入しています。
三菱マヒンドラ農機
三菱マヒンドラ農機は、三菱農機とインドのマヒンドラ&マヒンドラ社との合弁会社です。
三菱マヒンドラ農機の強みは、インドの大手企業であるマヒンドラ&マヒンドラ社の世界規模の視点と、三菱農機が長年にわたり培ってきた高度な技術力が融合している点にあります。
この両社の強みを活かすことで、革新的な農機の開発を実現しています。
自脱型と普通型のコンバインを販売しており、日本国内はもちろん、海外の農業にも対応できるように設計されています。
2018年に発表されたイーグルデザインを採用した新型コンバインは、その革新的なデザインで高い評価を得ました。
ヤンマー
ヤンマーは、ディーゼルエンジンの分野で高い技術力を持つメーカーとして知られています。
コンバインは、エンジン性能の高さと燃費の良さが特徴的で、長時間の作業でも安定した動作を提供します。中でも特筆すべき点は「自動ロス制御機能」です。
ヤンマーのコンバインに搭載されている自動ロス制御機能は、収穫作業におけるモミの損失を自動的に抑えてくれる技術です。この機能により使用者が熟練者でなくても、モミのロスを最小限に抑えた効率的な収穫が可能になります。
コンバインを選ぶ際の注意点について

コンバインを選ぶ際は、様々な要素を考慮する必要があります。
単に価格や馬力だけで選んでしまうと、後々後悔することになりまねません。
最も重要なのが圃場の規模と作物の種類です。(圃場:農作物を育てる場所)圃場の広さによって、最適なコンバインのサイズや性能は大きく異なります。狭い圃場では小回りが利き、軽量なコンバインが適しています。逆に、広大な圃場では、作業効率を重視した大型のコンバインが適しているでしょう。
また、水田で使用するのか畑で使用するのかによっても、選ぶべきコンバインの種類が変わってきます。稲作であれば自脱型、大豆やトウモロコシなどであれば普通型、複数の作物を育てている場合は汎用型が適しているでしょう。
そして、ランニングコストがかかることも考えましょう。
これは、コンバインに限った話ではないですが、機械は購入して終わりではありません。長期間使用していくためには、燃料や部品の交換など、定期的なメンテナンスが必要となるので、初期費用だけでなくランニングコストも考慮する必要があります。
それらを考慮すると中古コンバインを検討するのもありではないでしょうか。
まとめ
今回は、コンバインとは何なのか、自脱型・汎用型・普通型の種類ごとの違いなどを解説してきました。
コンバインは収穫・脱穀・選別を一台で行う農機で、作業効率を大幅に向上させます。種類は主に自脱型・汎用型・普通型の3種類です。
自脱型は日本の水田に適しており、稲や麦などの穂先のみを脱穀します。汎用型は刈取部を交換することで複数の作物に対応できますが、1つの作物に特化した種類と比べると効率は劣ります。
普通型は作物全体を取り込んで脱穀します。大規模の農場向けで、日本の水田には不向きです。
中古農機具はもちろん、コンバインを選ぶ際は、圃場の規模と育てる作物の種類によって適した種類を選びましょう。また、初期費用だけでなくランニングコストがかかることも考慮して選んでください。
コンバインを使用しているけども、新しいコンバインの購入を検討している。もし、コンバインの買取業者を迷っている方は、こちらから一括査定を依頼してみましょう。